平素より、格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
このたび、当協同組合は、2023年11月1日をもちまして、名称を「日本福祉人材協同組合」から「外国人材情報協同組合」に変更することとなりました。
今回の名称変更は、時代の変化に対応し、外国人材の活躍をより一層支援するため、新たなスタートを切る意味を込めて実施するものです。
今後とも、より一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。
はじめに
外国人材情報協同組合(旧称:日本福祉人材協同組合)は2020年4月に設立いたしました。
当組合は介護・福祉に特化した協同組合として設立後、より多くの事業者様のニーズにもお応えするべく、2023年11月よりその他業種の技能実習適合職種の受け入れも開始いたしました。
今後も相互扶助の精神で、組合員様のお役に立てるよう事業を行っております。
私たちが目指すもの
私たちは、技能実習の制度に沿って国際的な人づくりに携わることで、自らもまた成長してまいりたいと考えております。
外国人技能実習生を育成できる職場環境は、日本人を含む多様な人々を育成できる環境であると考えるからです。

技能実習では3年(条件によっては5年)、日本で技術を学ぶことができます。
その後実習生・受入れ事業者双方が合意することで特定技能として最大5年間就労が可能です。
※技能実習から特定技能に移行できない職種もあります。
また、私たちは介護職に対しては、実習実施期間の3年~8年の間に実務経験を活かし、介護福祉士の資格を取得できるようサポートいたします。
そして意欲・適性・能力のある外国人材が、それぞれの事業で活躍することを通じて、共に働く日本人スタッフとの交流、職場の活性化、人手不足の解消などの社会的課題の解決することにつながると考えております。
私たちの強み
介護・福祉事業者を中心とした協同組合です
事業者の相互扶助、地位向上を目的として設立された協同組合です。
技能実習生共同受入れ事業ですのでいろいろな介護事業者のノウハウを活かすことができます。
様々な外国人材活用例を持つ組合員も
技能実習だけでなく2019年に創設された特定技能、介護福祉士養成校に通う留学生、介護ビザの外国人など様々な外国人材活用経験を持つ組合員もおります。
そういった先行事例に学ぶことも当組合ならではの強みです。
組合員企業での例
制度について
技能実習制度の目的・趣旨は、日本で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することにあります。
また「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」と法令で明確に謳われてもいます。
介護職種は2017年に追加されましたが、上記の目的・趣旨の一環であることに変わりはありません。
対人サービスの実習に当たることから日本語能力やその他職種より厳しい受入れ人数枠等の要件は設けられていますが、実習計画に基づいて国際的な介護人材育成を行います。
各種制度や仕組みについては所管する団体のWebサイトをご参照ください。
・外国人技能実習機構
https://www.otit.go.jp/
・公益財団法人 国際人材協力機構
https://www.jitco.or.jp/
・出入国在留管理庁
http://www.moj.go.jp/isa/index.html
・一般社団法人 シルバーサービス振興会
http://www.espa.or.jp/
当組合受入れ実績国
 フィリピン |  インドネシア |
 ベトナム |  ミャンマー |
 中国 |
~技能実習介護から将来のリーダーへ~
当組合は意欲を持って入国してくる技能実習生に対し、日本で介護福祉士になり、永続的な就労はもとより、将来のリーダーとして活躍していただくことを願っております。
そのために私どもが大切にしていることは以下の四つです。
1.技能実習生への日本語学習支援
2.技能実習生への介護福祉士国家試験受験対策支援
3.技能実習生への生活支援と異文化理解促進
4.受入れ施設様へのコンサルティング
いい人材に長く勤めていただく、そのためにも技能実習制度が根幹としている「人づくり」を私どもは組合員の皆様とともに創ってまいります。
そして日本の介護の新たな地平を皆様とともに創造したいと考えております。
当組合の技能実習生に対する成長支援一例

日本語学習支援
現場で役に立つことを目的として、入国前から組合独自にオンラインで日本語学習コンテンツを提供しています。
オリジナルの確認テストも用いて意欲や習熟度も測ることができます。
実習生の多くが「最初は日本語がわからなくて困った」と言いますので、1日でも早く実習が円滑に進められるよう支援をいたします。
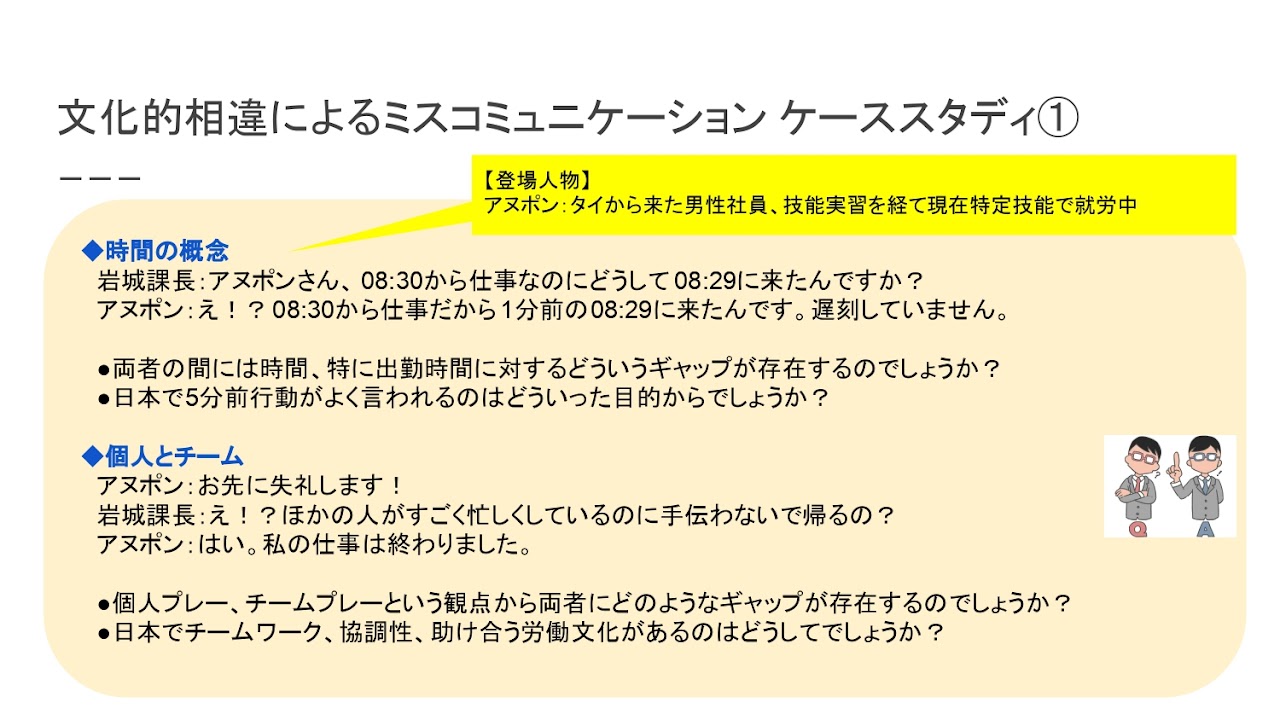
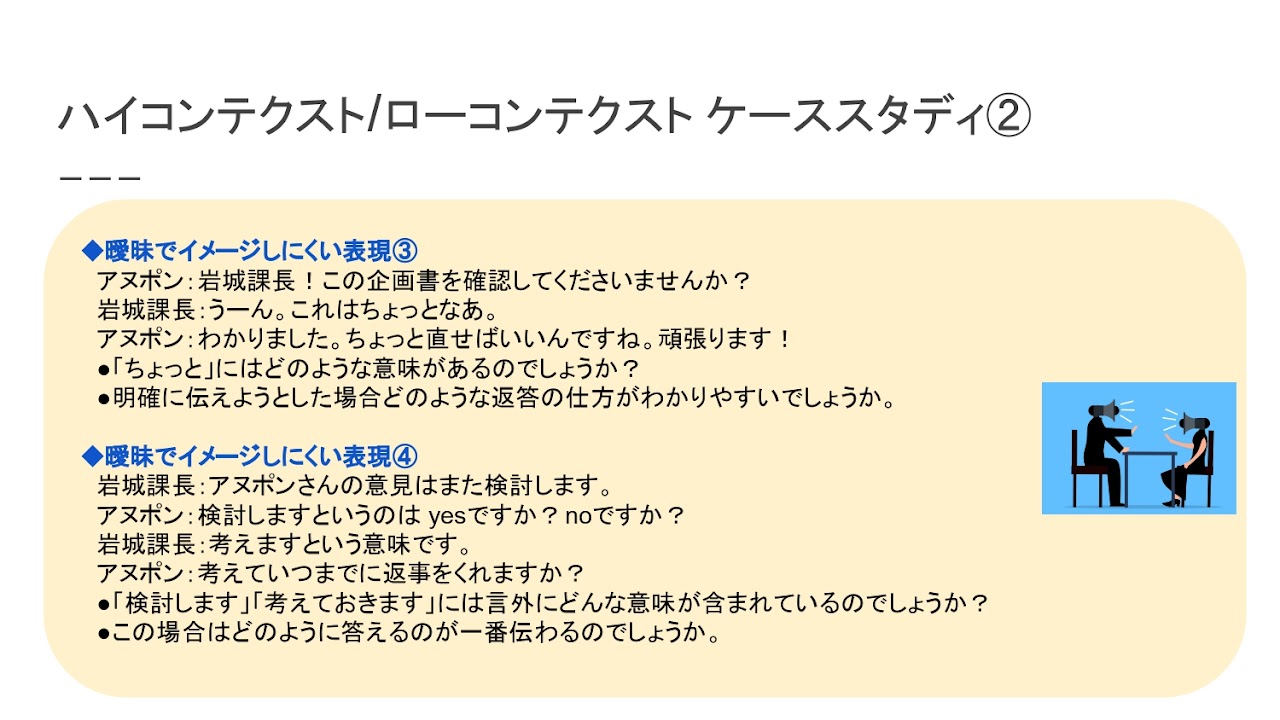
異文化理解促進
価値観や文化的相違など、目に見えない異文化間ギャップのために摩擦や感情的すれ違いが起こることもしばしばあります。
そういった失敗事例も盛り込んだケーススタディブックを当組合では資料にまとめました。
このような事例を皆様にも参考にしていただき、実習生ともども失敗から学び、異文化理解促進を支援いたします。
